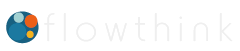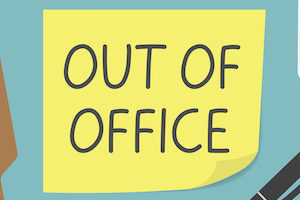(前回のつづき)
問題にどの地点で気づくかで、対処方法は変わる
つぎに、問題発生に気づくタイミングによって対処方法が異なることを説明する。
タイミングは問題の発生前、発生中、発生後の3つの時期のどれかとなる。
問題発生前の対処「検知」
問題発生前には何が起きるかはわからない。
そこで、普段とは違う数字の変化だったり、なんとなくの空気感だったり、問題が起きる前触れを「検知」することが重要となる。
検知の精度は経験を積めば向上していき、問題が発生する前の、軽微な段階で対処が可能になる。
そして、重要性の高い問題が発生することが少ない組織が出来上がっていく。
検知の仕組みは、会計システムによる数字の変化を示す警報だったり、従業員の不満を吸い上げる仕組み、最近だとITやセンサーを活用したデータ分析など様々なものがある。
もっとも「検知」を100%にすることはできない。100%を目指せば膨大なコストがかかって現実的ではないからだ。
問題発生中の対処「初期消火」
検知による予防にもかかわらず問題が発生してしまったら、次は「初期消火」を行うことになる。
問題の頻度や重要性を把握し、解決のための具体的な行動を取る。
初期消火は「すばやく、確実に」行う。
この段階での対処を間違えると、問題が他の部分に飛び火(延焼)したり、消火したつもりが小さな火種が残り後日再び炎上するといったことになる。
また、問題を解決した結果、新たな問題が発生する・・・ということもよくある。
営業管理の問題を解決するためにシステムを導入したら、入力に時間が取られて営業マンの顧客訪問効率が落ち、売上が下がってしまうなどがその例だ。
初期消火を間違ってしまったのだ。
問題発生後の対処「恒久的対処」
問題がある程度解決したら、次に同じ問題が発生した場合にどうするか、つまり「恒久的対処」を検討することになる。
初期消火はスピード重視だが、恒久的対処では問題発生の原因を見極め、二度と発生しない、もしくは発生してもその影響を最小限に留めるための仕組みづくりを重視する。
恒久的対処の方法が決定すれば、「検知」の方法も変わるだろう。
今回発生した問題の兆候を検知するための新たなチェック項目が増えるかもしれない。
また、これまで重要だと思っていた項目が役に立たないことがわかり、チェック項目から削除されることもある。