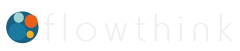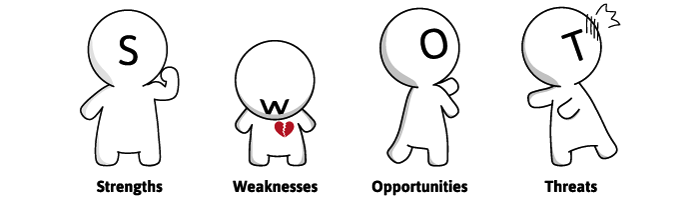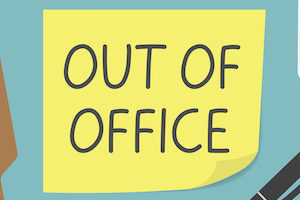先日読んだ本からの引用。
名目賃金や実質賃金といった経済統計について留意すべきは、
それらの指数を導き出すための調査では
従業員5人未満の事業所は対象となっていないということです。端的にいうと、経済的な苦境にもっとも追いやられた
零細企業の実態が、名目賃金や実質賃金の調査には反映されていないのです。
-日本の国難 中原圭介著
名目賃金や実質賃金のデータを見て、
「改善しているな」と思っていた。
しかし、それはあくまで大企業や中堅企業の話であって、
5人未満の事業所(つまり、小規模事業者)はそもそも
カウントされていないらしい。
ということは、現実社会の一部を切り取ったものであり、
全体を反映しているものではない、ということだ。
データを見るときには、
それを作成するために集めた「元データ」まで
考慮しないと、判断をまちがってしまう。
アンケート結果なども同じだ。
偏った母集団から集めたデータは、やっぱり偏ってしまう。
また、質問の文章の書き方、質問の順番、選択肢の作り方ひとつで
その結果は容易に変わってしまう。
結果だけを見て何かを判断するのは早計だ。
そのデータの母集団は何か?
どのような方法で集められたものか?
そこまで理解して初めて、
「活きたデータ」になる。