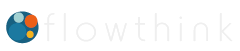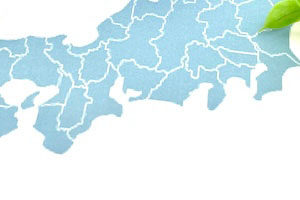「社会人の基本」と言えば、何を思い浮かべるだろうか?
ホウレンソウ(報告・連絡・相談)や、5W1Hを先輩に口酸っぱく指導された記憶がある人は多いだろう。
5W1Hは初心者向けの考え方に留まらない、あらゆる文書や会話を論理的にかつ抜け漏れなくするための有益なものだ。
誰もが知っているこの5W1Hについて筆者なりに掘り下げてみたい。
5W1Hとは
もともとは「5W」だったようだ。
語源は英語で、Wikipedia日本語版および世界大百科事典によれば、
ニュース記事のリード文書くときのルールから始まったとある。
重要な要素を端的に伝えるために、
When(いつ)、Who(だれが)、Where(どこで)、Why(なぜ)、What(何を)の
頭文字である5つのWから「5W」と呼ばれるようになった。
5W1H
5WにはWhat(何を)が入っている。
何をすればいいのかはわかる。
しかし、それをどうやったらいいのかはわからない。
ダイエットをする(何を)のはわかるけれど、どんな方法で(どうやって)がわからない。
そこで、How(どうやって)を加えたものを「5W1H」と呼ぶ。これが一番ポピュラーなようだ。
5W2H、3H、4H
また、5W1HにさらにHow Much(いくらの値段で)を加えて「5W2H」として使うこともある。
何をやるにしてもコストの観点は避けて通れないだろう。
他にも、How Long(どれくらいの期間で)や、
How Many(どれくらいの量を)を加えて、5W3H、5W4Hとすることもある。
6W
5WにもうひとつW(Whom、だれに)を加えて6Wと言うこともある。
誰に伝えるのか、その相手によって内容は変わるからだ。
ここでは、全ての要素を網羅した「6W4H」について説明する。
もちろん常に6W4Hを意識する必要は無い。
対象によっては省略できる要素もあるので、状況により要素を増減させつつ使うのが正しい。
(つづく)