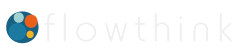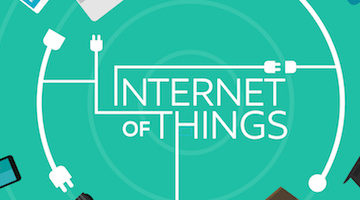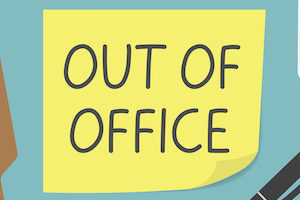「その言葉の定義は?」と発言すると、3割くらいの確率でウザがられてしまう。
気の弱い私は、そのたびに申し訳ない気持ちになる。
それでもやらなければならない。
言葉の解釈は人によって大きくブレる
言葉の解釈は人によって大きくブレることがある。
同じ職種だったり、同じ会社で働いていればその差異は小さく、気づかない程度だ。
しかし、異業種・異文化に属する人とのやりとりだとその差異は顕著になる。
たとえば「デザイン」という言葉がある。
この言葉の意味は広く、単純に見た目を指すこともあれば、仕組み・体系といった大きな概念を意味することもある。
相手が何を想定して「デザイン」と言っているかを確認しなければ、実りあるコミュニケーションを取ることは困難だろう。
(個人的には横文字の言葉にこういった意味を広く取れる言葉が多いと思う)
最初に定義を合わせるのが結局は効率的
いちいち言葉の定義を確認しつつ議論を進めるのは、正直いってしんどい。
相手からも嫌がられることがあるし、非効率な気がすることもあるだろう。
しかし、やらなければならない。
議論の初期にこの作業を済ませておけば、後のトラブルを避けることができる。
あいまいな議論からは、あいまいな結論しか生まれない。
言葉の定義を厳密に、研ぎ澄ませることが、良い議論を行うための「最初の一歩」だ。