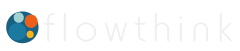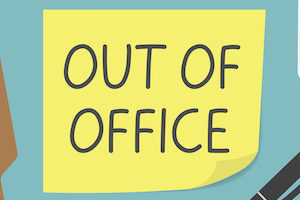十日恵比須に行ってきた。
福岡市近郊以外の方向けに捕捉すると、
10日前後に福岡市東公園内にある神社で行われるお祭りで、
福岡で商売をしている人のほとんどが参拝するというものだ。
大学時代を福岡で過ごしたが、
このお祭りの存在を知らなかった。
社会人になって、大企業の福岡支社で
働いていた時も知らなかった。
このお祭りの存在を知ったのは、
福岡地場の会社に転職してからだ。
私の観測できる範囲では、
同じ福岡県といっても北九州市や久留米市の方には
あまりなじみがないようなので、
福岡市とその近辺だけのローカルなお祭りなのだろう。
福引き(2千円)が特徴で、くじに応じて
おめでたい感がたっぷりの景品が当たる。
今回は熊手だった。
いつ参拝するかで商売へのスタンスがわかるような
毎年、早朝6時頃に参拝している。
お祭りは4日間行われ、深夜まで人の流れが途切れない。
ただ、早朝であれば並ばずに参拝と福引きができる。
今回は天気も悪かったからか、すぐにお参りできた。
1月、仕事始めの忙しい時期に行列で時間を潰したくないので、
いつも朝に来ている。
友人の経営者達と混み合った時間帯に
行列に並んで参拝するのも
ひとつのエンターテインメントだと思うし、
それはそれで楽しいのではあるけれど、
なぜか1月は忙しいことが多い。
仲間と連れ立って参拝する経営者、
一人で来る経営者。
空いた時間に来る経営者、
混み合った時間に楽しんで行列に並ぶ経営者。
商売の神様だからというわけではないが、
参拝一つとっても、経営者の商売に関するスタンスも出ているのかなと思う。
#もちろん、時間の都合で選択肢のない人も居るだろう。
ビジネスモデルの強さ
ここの福引きシステム(敢えてそう言う)は、
素晴らしいビジネスモデルだ。
江戸時代からあるのだろうか?
お賽銭は金額をコントロールできないけれど、
福引きなら価格設定もできて、
原価計算も容易だ。
何より、縁起物ということで
顧客は支払いを惜しまない。
むしろ喜んでお金を出している。
関係者に聞くと、この4日間で数億円の売上(この言葉が適切かどうかはわからない)が上がるそうだ。
一見非合理なことの合理性
参拝したくらいで商売が上手くいくなら苦労はない。
去年この神社に参拝した福岡の経営者も、
おそらく何人もが破産の憂き目にあっただろう。
では、参拝することは非合理的だろうか?
それは違う。
福岡市内およびその近郊の商売人が皆参拝している、
同じ文化を共有しているということに意味がある。
一見不合理だけれど、そこには同じ地域でビジネスを
しているものたちの仲間、共同体に参加しているという表明であり、
商売を円滑に進めるための一種の儀式の役割を果たしている。
単純に参拝だけを見れば非合理的だけれど、
少し視点を広げれば、合理的な行動がそこに見えてくる。
まあ、こんなことをつらつら考えるのは
理屈っぽい経営コンサルタント(中小企業診断士)くらいなもので、
単純に新年を祝いつつ、福引きと露店を楽しめば、それでいいのだろう。